力学の問題を考えるときに必要な座標設定はいろいろあります
・斜面を滑るブロックを考えるなら、斜面に沿った方向に軸をとる
・振り子を考えるなら、極座標をとる
といった感じですよね、今回はこのような問題ごとに様々な座標設定を運動の自由度に注目して統一的に扱う方法の一つであるラグランジュ方程式を導きたいと思います
1.運動の3法則
まずは力学を考えるにあたって、その出発点となる3つの「当たり前とされていること」があります
- 慣性の法則
➡ 物体に力が働いていなければ、物体の運動は変化しない - 運動方程式
➡ \(m \boldsymbol{a} = \boldsymbol{F}\) - 作用・反作用の法則
➡ 他の物体に力を加えると、その力と大きさが等しく逆向きの力を同じ作用線上で受ける
実際に運動を解析する場合には、二つ目の運動方程式を解くことになります
運動方程式を立てるのに必要な加速度と力はベクトルなので、座標系の取り方によって成分表示が変わってしまうことが少々めんどうですね
そこで座標系の取り方を変えても、統一的に扱える別の形の運動方程式があると、それはそれは便利なわけです
その便利な形のひとつというのがラグランジュ方程式になるわけであります
さて、ラグランジュ方程式を導くための準備として、
- ダランベールの原理
- 仮想仕事の原理
を知っておく必要があるので、まずその2つから説明したいと思います。
2.ダランベールの原理
最初はダランベールの原理からです
まず運動方程式の形をちょこっと変形して
\[m \boldsymbol{a} – \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0} \]
としてみると、\(\boldsymbol{F}\) を移項しただけですが、この式をこういう風に見てみます
\(m \boldsymbol{a}\) という力と、\(- \boldsymbol{F}\) という力を受けているが、それらが\(\boldsymbol{0}\) となって釣り合っている
するとどうでしょう、運動状態を表す運動方程式を、力のつり合いの式として見ることができるんですね
このように運動方程式を釣り合いの式として見なした形、あるいはそのように見なせることをダランベールの原理と言います
要は慣性力を導入して釣り合いと見なしているわけですね
3.仮想仕事の原理
次に仮想仕事の原理です
系がつり合っているとき、その状態から運動が可能な方向に少し動かしても、仕事は0
逆に、運動が可能な方向に少し動かして仕事が0なとき、系はつり合っている
ということです
これは式で見るとかなり当たり前のもので
運動が可能な方向に少し動かしたその変化量を\(\delta x\) と書くことにすると
\[\sum_{n = 1}^{N} \boldsymbol{F}_{n} = \boldsymbol{0} \Leftrightarrow \sum_{n = 1}^{N} \boldsymbol{F}_{n} \cdot \delta x= \boldsymbol{0} \]
というだけのことなんですね、つり合いの式に\(\delta x\) をかけても0のままです
4.ラグランジュ方程式
それではいよいよラグランジュ方程式を導出したいと思います
状況設定としては、\(N\) 個の粒子があり、\(i\) 番目の粒子の座標が\((x_{i}, y_{i}, z_{i})\) だという感じです
その上で、系の自由度は\(A\) であるとします
単純にニュートンの運動方程式\(m \boldsymbol{a} = \boldsymbol{F}\) を立てると、\(N\) 粒子それぞれに\((x, y, z)\) で3つずつ、計\(3N\) 個の式を立てる必要がありますが、今系の自由度は\(A\) なので、\(A\) 個の式で十分なはずです
このように従属、独立が混じっている\(3N\) 個の変数を、独立な\(A\) 個の変数にそぎ落とすと、扱いやすいですね
この自由度分の独立変数で記述された運動方程式の一般的な形がラグランジュ方程式です
それではまずダランベールの原理から、\(\boldsymbol{r_{i}} := (x_{i}, y_{i}, z_{i})\) として
\[\sum_{i = 1}^{N} m \ddot{\boldsymbol{r_{i}}} – \boldsymbol{F_{i}} = \boldsymbol{0}\]
これはつり合いの式なので、さらに仮想仕事の原理から
\[\sum_{i = 1}^{N} [m \ddot{\boldsymbol{r_{i}}} – \boldsymbol{F_{i}}] \cdot \delta \boldsymbol{r_{i}}= \boldsymbol{0}\]
となります
さてこの式をこれからゴリゴリ変形していきます
今自由度\(A\) だけで表したいですので、その数だけ新たに独立変数\(q_{1}, q_{2}, \cdots, q_{A}\) をとります、これを用いて
\[\boldsymbol{r_{i}} = \boldsymbol{r_{i}}(q_{1}, q_{2}, \cdots, q_{A};t) \]
と書き直すことができます、すると1次近似をすると,変数\(q_a\ (a = 1,\cdots,A)\)についての変分がでてきて
\[\begin{eqnarray} \delta \boldsymbol{r_{i}} &=& \boldsymbol{r_{i}}(q_{1} + \delta q_{1}, q_{2} + \delta q_{2}, \cdots, q_{A} + \delta q_{A};t) – \boldsymbol{r_{i}}(q_{1}, q_{2}, \cdots, q_{A};t) \\ &=& \sum_{a = 1}^{A} \frac{\partial \boldsymbol{r_{i}}}{\partial q_{a}} \delta q_{a} \end{eqnarray}\]
となって、まずは\(\delta \boldsymbol{r_{i}}\) を自由度分の独立変数だけで表すことができました
さらに\(\dot{\boldsymbol{r_{i}}}\) と\(\delta \dot{\boldsymbol{r_{i}}}\) も自由度分の独立変数\(q_{1}, q_{2}, \cdots, q_{A}\) で表したいと思います
\[\dot{\boldsymbol{r_{i}}} = \sum_{a = 1}^{A} \frac{\partial \boldsymbol{r_{i}}}{\partial q_{a}} \delta \dot{q_{a}} + \frac{\partial\boldsymbol{r_{i}}}{\partial t}\]
これは単純に時間微分ですね
この結果から
\[\dot{\boldsymbol{r_{i}}} = \dot{\boldsymbol{r_{i}}}(q_{1}, \cdots, q_{A}, \dot{q_{1}}, \cdots, \dot{q_{A}}; t) \]
であることが分かりますので、1次近似すると,こちらは変数\(q_a, \dot{q}_a\ (a = 1,\cdots,A)\)についての変分がでてきて
\begin{align*}
\delta \dot{\boldsymbol{r_i}} &= \dot{\boldsymbol{r_{i}}}(q_{1} + \delta q_{1}, q_{2} + \delta q_{2}, \cdots, q_{A} + \delta q_{A},\ \dot{q}_{1} + \delta \dot{q}_{1}, \dot{q}_{2} + \delta \dot{q}_{2}, \cdots, \dot{q}_{A} + \delta \dot{q}_{A};t)\\
&\quad – \dot{\boldsymbol{r_{i}}}(q_{1}, q_{2}, \cdots, q_{A},\ \dot{q}_{1}, \dot{q}_{2}, \cdots, \dot{q}_{A};t) \\
&= \sum_{a = 1}^{A} \frac{\partial \dot{\boldsymbol{r_{i}}}}{\partial q_{a}} \delta q_{a} + \sum_{a = 1}^{A} \frac{\partial \dot{\boldsymbol{r_{i}}}}{\partial \dot{q}_{a}} \delta \dot{q}_{a}
\end{align*}
となります.さてではこれらを用いてダランベールの原理を変形していくことにします.
基本理念は自由度\(A\)のみでの表式に帰着させることです.
\(\boldsymbol{F}_i \cdot \delta \boldsymbol{r}_i\)について
ダランベールの式
\[\sum_{n = 1}^{N} \left( m \ddot{\boldsymbol{r_{i}}} – \boldsymbol{F_{i}}\right) \cdot \delta \boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{0}\]
の左辺の第2項についてみていきます.
\begin{align*}
\sum_{i} \boldsymbol{F}_i \cdot \delta \boldsymbol{r}_i
\end{align*}
さきほど導いた\(\delta\boldsymbol{r}_i\)の一次近似の形を用いると,
\begin{align*}
\sum_{i} \boldsymbol{F}_i \cdot \delta \boldsymbol{r}_i &= \sum_a \sum_i \boldsymbol{F}_i \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_a} \delta q_a
\end{align*}
ここで
\[Q_a = \sum_i \boldsymbol{F}_i \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_a}\]
を一般化力とよび,これを用いると
\begin{align*}
\sum_{i} \boldsymbol{F}_i \cdot \delta \boldsymbol{r}_i &= \sum_a Q_a \delta q_a
\end{align*}
となって自由度\(A\)のみに基づいた形で表すことができます.
\(\sum_i m_i \ddot{\boldsymbol{r_{i}}} \cdot \delta \boldsymbol{r}_i\)について
ダランベールの式
\[\sum_{n = 1}^{N} \left( m \ddot{\boldsymbol{r_{i}}} – \boldsymbol{F_{i}}\right) \cdot \delta \boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{0}\]
の左辺の第1項についてみていきます.
こちらは計算がめんどうな部分がありますので,少し準備していきます.
時間微分と\(q_a\)微分の順番を交換してよいことの確認
\begin{align*}
\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial q_a} \boldsymbol{r}_i &= \sum_b \frac{\partial}{\partial q_b}\dot{q}_b\frac{\partial}{\partial q_a} \boldsymbol{r}_i + \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial}{\partial q_a} \boldsymbol{r}_i \\
&= \frac{\partial}{\partial q_a}\left(\sum_b \frac{\partial}{\partial q_b}\dot{q}_b \boldsymbol{r}_i +\frac{\partial}{\partial t} \boldsymbol{r}_i \right) \\
&= \frac{\partial}{\partial q_a} \frac{d}{dt} \boldsymbol{r}_i
\end{align*}
ということで時間変数と自由度については微分の順番が交換できることがわかりました.
\(q_a \)微分と\(\dot{q}_a \)微分の関係
\begin{align*}
\dot{\boldsymbol{r_{i}}} = \sum_{a = 1}^{A} \frac{\partial \boldsymbol{r_{i}}}{\partial q_{a}} \delta \dot{q_{a}} + \frac{\partial\boldsymbol{r_{i}}}{\partial t}
\end{align*}
というのが時間微分の計算から導かれましたが,各\(\dot{q}_a\)の独立性から,\(\dot{q}_b\)で両辺を微分すると,右辺は\(\dot{q}_b\)を持つ項以外消えるので,
\[\frac{\partial \dot{\boldsymbol{r_{i}}}}{\partial \dot{q}_b} = \frac{\partial \boldsymbol{r_i}}{\partial q_b}\]
となって,あたかも分母分子の時間微分が約分できたみたいに計算することができます.
\(m_i \ddot{\boldsymbol{r_{i}}} \cdot \delta \boldsymbol{r}_i\)について
\begin{align*}
m_i \ddot{\boldsymbol{r_{i}}} \cdot \delta \boldsymbol{r}_i &= \sum_a m_i \ddot{\boldsymbol{r_{i}}} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_a}\delta q_a\\
&= \sum_a m_i \left(
\frac{d}{dt}\left(\dot{\boldsymbol{r}_i} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_a} \right) – \dot{\boldsymbol{r}_i} \cdot \frac{d}{dt}\frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_a}
\right) \delta q_a\\
&= \sum_a m_i \left(
\frac{d}{dt}\left(\dot{\boldsymbol{r}_i} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_a} \right) – \dot{\boldsymbol{r}_i} \cdot \frac{\partial}{\partial q_a}
\frac{d}{dt} \boldsymbol{r}_i \right) \delta q_a\\
&= \sum_a m_i \left(
\frac{d}{dt}\left(\dot{\boldsymbol{r}_i} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{\dot{r}}_i}{\partial \dot{q}_a} \right) – \dot{\boldsymbol{r}_i} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{\dot{r}}_i}{\partial q_a}
\right) \delta q_a\\
&= \sum_a \left(
\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_a}\frac{1}{2}m_i \boldsymbol{\dot{r}}_i^2 \right) – \frac{\partial}{\partial q_a} \frac{1}{2}m_i \boldsymbol{\dot{r}}_i^2
\right) \delta q_a
\end{align*}
となります.ここで粒子の運動エネルギーを
\[T_i = \frac{1}{2}m_i \boldsymbol{\dot{r}}_i^2\]
とおくと,
\[m_i \ddot{\boldsymbol{r_{i}}} \cdot \delta \boldsymbol{r}_i = \sum_a \left(
\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_a}T_i \right) – \frac{\partial}{\partial q_a} T_i
\right) \delta q_a\]
という式を得ることができます.この時点ですでにかなりラグランジュ方程式っぽくなりました.
ラグランジュ方程式の導出
さてさてダランベールの式から出発して,今まで導いてきた式をつかってラグランジュ方程式を導きましょう.
全粒子の運動エネルギーの総和を\(T = \sum_i T_i\)と置くことにします.
\begin{align*}
0 = \sum_{i = 1}^{N} \left( m_i \ddot{\boldsymbol{r_{i}}} – \boldsymbol{F_{i}}\right) \cdot \delta \boldsymbol{r}_i
&= \sum_{i = 1}^N m_i \ddot{\boldsymbol{r_{i}}} \cdot \delta \boldsymbol{r}_i – \sum_{i = 1}^N \boldsymbol{F_{i}} \cdot \delta \boldsymbol{r}_i\\
&= \sum_a \sum_i\left(
\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_a}T_i \right) – \frac{\partial}{\partial q_a} T_i
\right) \delta q_a – \sum_a Q_a \delta q_a\\
&= \sum_a \left(
\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_a}T \right) – \frac{\partial}{\partial q_a} T – Q_a \right) \delta q_a
\end{align*}
ここで自由度の変化分\(\delta q_a\)は十分小さい範囲ですべて任意にとれることに注意すると,
この式が成り立つには,つまり和が0の条件を満たすには,中身が0であることが必要ですから,
\[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_a}T \right) – \frac{\partial}{\partial q_a} T – Q_a = 0\]
が成り立ちます.
では外力\(\boldsymbol{F}\)がポテンシャル\(U = U(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N)\)によって
\[\boldsymbol{F} = – \nabla U\]
と表される状況を考えましょう.このとき一般化力は
\begin{align*}
Q_a &= \sum_i \boldsymbol{F}_i \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_a}\\
&= – \sum_i \nabla U \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q_a}\\
&= – \sum_i \left(
\frac{\partial U}{\partial x_i}\frac{\partial x_i}{\partial q_a} + \frac{\partial U}{\partial y_i}\frac{\partial y_i}{\partial q_a} + \frac{\partial U}{\partial z_i}\frac{\partial z_i}{\partial q_a}
\right)\\
&= -\frac{\partial U}{\partial q_a}
\end{align*}
とかけます.また\(U\)は\(q_a\ (a= 1, \cdots, A)には依存しますが,\dot{q}_a(a= 1, \cdots, A)\)には依存しないので,
\[\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_a} = 0\]
となります.よって
\[L = T – U\]
とおくと,
\[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_a}L \right) – \frac{\partial}{\partial q_a} L= 0\]
これでラグランジュ方程式が導けました.
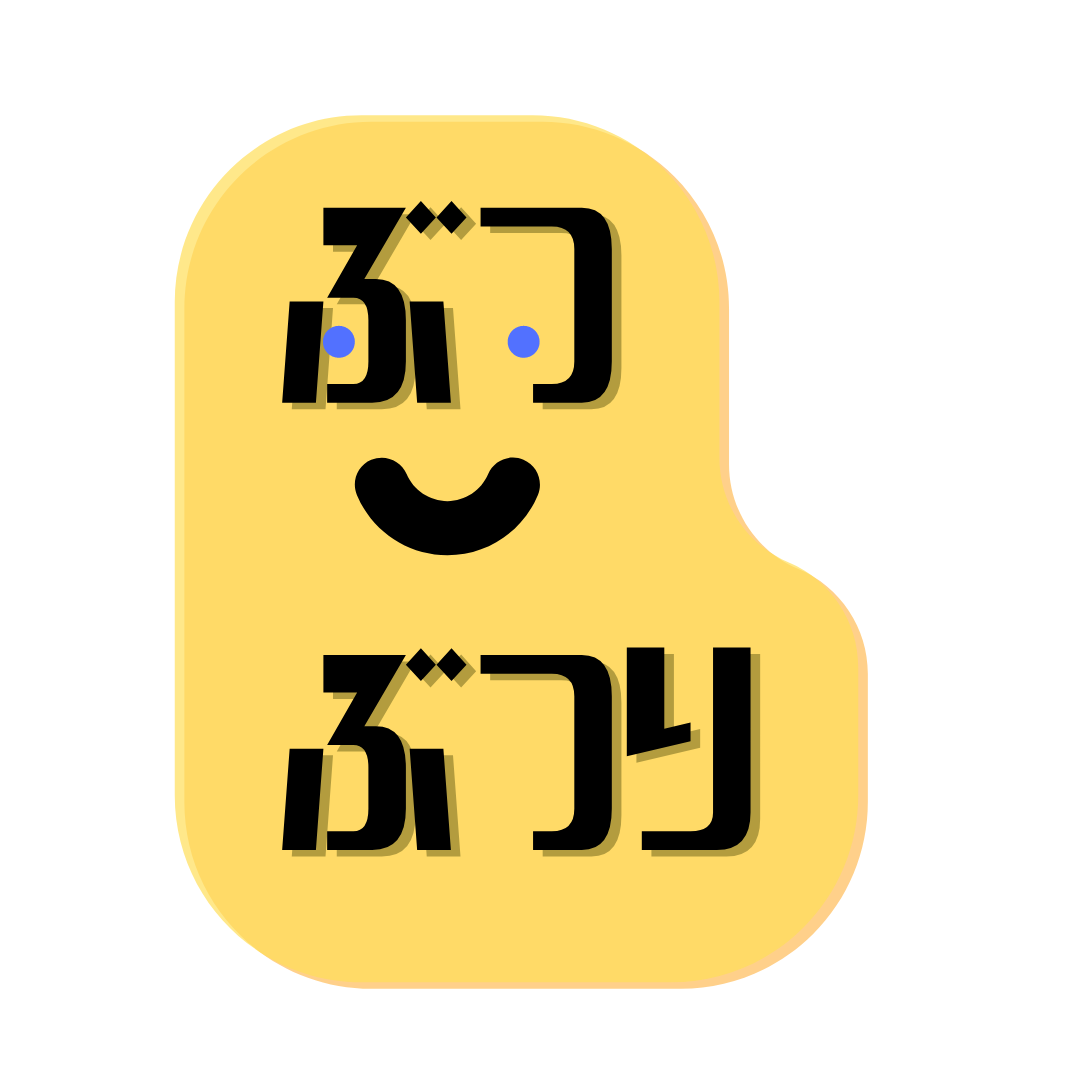
最後までお読みいただきありがとうございました

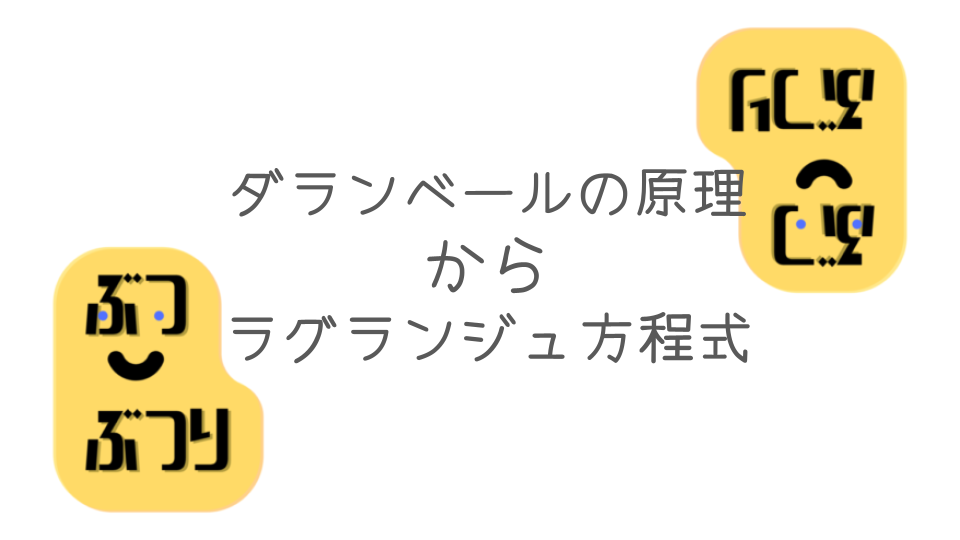
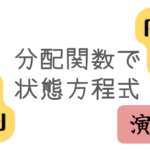
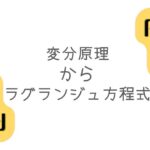
コメント